2025年2月、NanoTerasu 国際共創利用支援制度を利用してNanoTerasu で実験中の、ローマ大学の鶴巻晃子助教と有機・バイオナノ材料研究分野の岡弘樹講師にお話を伺いました。

今回の共同研究のきっかけは?
岡弘樹:2024年6月に、ローマ大主催の若手の学会で、キーノートレクチャーの講演者として、共通の知人を通して声を掛けてもらったのがきっかけですね。
鶴巻晃子:学会開催まで2か月もないときに、急にお願いしたんですが、岡先生が時間を作って引き受けて下さったんです。
岡:有機・バイオナノ材料研究分野から参加した博士学生と一緒に、ローマ大学を案内してもらいながら、共同研究したいねって話をしていたんですよね。鶴巻さんは電解液の研究をしているので、電池の中身を詳しく調べてみたいと話していたんです。僕は電極の研究をしていますから、組み合わせて共同研究できないかなって話をしていたところだったんです。9月に今回のプログラムの募集があったので、一緒に応募しました。
東北大学のこの支援プログラムは、ナノテラスの利用料と今回の測定に関係している試薬の購入の他に、旅費にも使えました。スケジュールも、鶴巻さんの日程に柔軟に合わせてもらえましたし、この支援があったからこそ、実現できたことです。
今回のスケジュールは?
鶴巻:2週間で、8時間ずつのビームタイムを5回予定しています。毎日実験が入っているわけではないので、東北大学や、母校の東京農工大学を訪問してディスカッションするなど、有効に使わせていただいています。今日は、今から実験の予定です。
岡:ビームタイムは8時間ずつのシフトなので、夜中2時からというのもあるんですよね。今日はいい時間帯です。研究者が自分で使える装置と、担当のテクニシャンの方がずっと付いていてくださる装置があるんですが、今日は、僕たちだけで使える装置です。
NanoTerasu で実験してみて…
鶴巻:いやもうすごいです!測定のスピードにびっくりしました。
岡:XRDという装置を使って、8時間ずつ2日間かける予定だった実験が、1日で全部終わりました。超高性能ですね。大学のラボにある装置で2~30分かかる測定が、NanoTerasuを使うと1秒です。
鶴巻:今回、だいぶ勝手が分かったのでよかったです。実際に触ってみないと分からないことが多かったと思います。イタリアにも放射光施設があるのですが、行ったことはなかったんです。NanoTerasuは、場所もいいですね。昨日も、学生さんたちと話していました。「都会からこんなに近いところにシンクロトロンの設備があるなんて!」って。
岡:昨日、研究室の学生に、鶴巻さんが実験しているところを見学してもらったんです。事前に申請すれば、見学もできます。「ハッチ」と呼ばれる放射光が出るすぐ近くまで行く人以外は、放射線バッチも付けなくていいんです。
鶴巻:エレベーターは顔認証でしたね。休憩スペースや仮眠室もありました。
岡:海外の方でも簡単な手続きで使えるのもいいですね。通常は、放射線業務従事者登録などが厳しいんですが、NanoTerasuは、登録している人がついていれば、登録しなくても「一時立入者」として使えました。測定するサンプルを事前に登録して審査していただく手続きもスムーズでした。
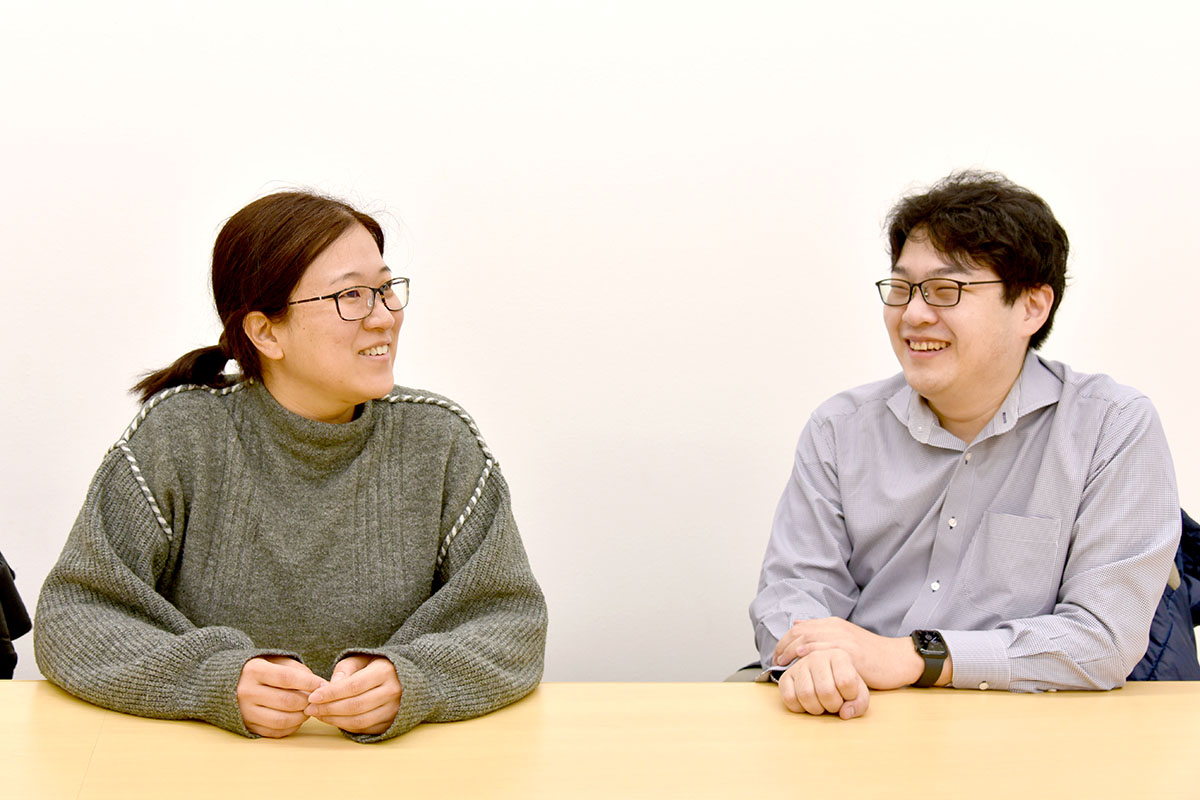
今後の目標は?
鶴巻:「より安全な電池を作りたい」というのが、私の研究の目標です。特に電解質と電極の組み合わせですね。材料については、かなり研究が進んでいますが、それを組み合わせた時の、界面の状態については、まだはっきりしていないところが多いので、どんどん解析していきたいと思っています。
岡:今回、その界面の分析をNanoTerasuで行いましたよね。
鶴巻:電極の中に金属イオンが入っているのですが、電池を使ってるうちに、だんだんと電解液の方に溶け出していってしまうんですね。今回は、それを防ぐために電極の中に混ぜ込んである微量な元素がどうなっているのか、電極と電解液の界面の状態を調べました。
岡:今回の研究を続けて、さらに理解を深めていきたいですね。ローマ大学の他の研究者の方とも密接なコミュニケーションをとって、国際連携を進めたいと考えています。
▶ 2024年度のNanoTerasu 国際共創利用支援制度採択研究課題
イオン液体で安定化された正極‐電解質界面の post-mortem と In-situ XRD 解析
鶴巻晃子氏:2015年3月 東京農工大学 博士課程修了、ローマ大学にて博士研究員などを経てRTD-A 研究員。2021年4月より。博士(工学)。( プロフィール詳細 )
取材日:2025年2月18日