本研究分野ではナノハイブリッド素材の創製について研究活動を行っている.2006年の研究活動としては,以下のように概括される.
1.雰囲気制御型PLD(Pulsed Laser Deposition)法による可視光応答型光触媒薄膜材料の合成と気相還元選択析出法(CVRD)による新規薄膜触媒の創製
遷移金属化合物の薄膜を種々の方法を用いて形態および組成を精密に制御して作製するとともに,薄膜の機能評価を行った. Nd:YAGパルスレーザーを用いるアブレーション法によるチタン酸化物薄膜の作製を行ない,レーザーのエネルギー,照射時間など照射条件と膜厚や構造との関係を明らかにするとともに,得られた薄膜の相関係,膜厚,形態について調べた.また,CH3CN,CS2を用いてin situで薄膜の窒化処理、硫化処理を行うとUV吸収特性が可視光側へシフトすることがわかった.
さらに,この薄膜上に新しく開発した気相還元選択析出法を用いて,Niナノ粒子を選択析出させることに成功し,光触媒活性の向上を確認した.
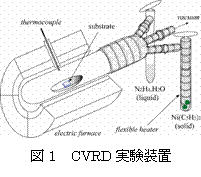
2.チタノシリケートの新合成法の開発
高い機能性材料として知られているゼオライトのうち、チタノシリケートの新合成法を開発した。すなわち、チタニアとシリカの固体粉末を遊星ボールミルで粉砕することにより非晶質出発物質を調製し、これに構造指向剤(structure-directing agent, SDA)を加え、高温処理して結晶化させることでチタノシリケートを得た。従来法では非常に高価な金属アルコキシドを出発物質としており、本手法の開発により、チタノシリケートの実用化が進展することが期待される。
3. 構造指向剤の複合化による新規ゼオライト合成
近年,高機能触媒や高性能吸着剤への応用を狙った新規構造ゼオライトの合成研究が盛んになされている.しかし,それらの研究では複雑な構造を持つ有機化合物がSDAとして用いられることが多く,製造コストが高くなるため,工業的な利用には不利である.そこで本研究では,容易に入手あるいは合成が可能で,比較的安価な有機化合物2種を複合してSDAとして用いることによりゼオライト合成を行い,得られた物質に対してキャラクタリゼーションを行った.その結果,2種のSDAを複合化して用いた場合,これら両生成物の物理混合物ではなく,新たな相が得られることがわかった.
4.液相還元選択析出法によるNi-Zn/TiO2ナノコンポジット粒子の合成
液相還元法によって調製した金属ナノ粒子触媒はその高い表面活性のために反応中凝集,凝結して失活することが多いが,適当な担体に担持することによって防止できる.本研究では,アモルファスNi-Znナノ粒子をアナタースチタニアナノ粒子上に,選択的に還元析出させる新しい触媒調製法を開発した.Niナノ粒子のサイズはZn添加量の増加とともに小さくなり,等モルのときに1~2 nmまでに至った.このナノ粒子はチタニア上できわめて安定であり,Niとして初めて安定なシングルナノ粒子が合成できたものと考えられる.
5.液相還元選択析出法による新規Pd系触媒の調製
Pd系合金触媒材料はC4化学において高い触媒活性を示すことが知られているが, 反応中において元素が溶出し失活するという問題が報告されている.これは触媒材料中において様々な種類の合金が共存していること(不均質性)及びその結晶性が低いためであると考えられている. また、原子レベルで均一で結晶性の良い合金ナノ粒子を合成するためには, 金属元素の還元・析出反応速度を厳密に制御することが重要となる. その為には, 溶液中において金属元素が均質な錯体構造を持つことが必要不可欠と考えられる. そこで本研究ではPd系触媒を選択し, 溶液中でのPd錯体構造計算を行い, 錯化剤の種類, pH及び反応温度と生成したPd系合金ナノ粒子の相関について検討した. また, 生成した粒子中のPd及びTeの状態や粒子径, 結晶性の程度についての詳細なキャラクタリゼーション及び実際に工業触媒として使用する場合に不可欠な担体への均一な担持方法の開発と, 触媒反応活性・安定性についても検討を行った.
6.単分散ヘマタイト粒子と有機液晶分子とのハイブリッド化
異種分野・物質の融合にもとづく境界領域の科学は,物質・材料の開発においてあらたなブレイクスルーをもたらすであろうとの期待から,近年特に脚光を浴びている.我々はこれまでに,有機物・無機微粒子それぞれの異方的な形状に着目し,有機無機ハイブリッド液晶を創製してきた.本研究では,“ゲル-ゾル法”をはじめとした無機微粒子作製技術により形状異方性を有する単分散 α-Fe2O3微粒子を合成し,得られた α-Fe2O3微粒子とリン酸基を有する有機液晶性分子を混合し,得られたハイブリッド体の組織構造および熱的挙動を調べた.
7.複合酸化物の部分硫化と光触媒への応用
TiO2の他,SrTiO3, BaTiO3,BaZrO3等の複合酸化物についても石英製のTG装置によりCS2+N2雰囲気中での硫化特性を解明した.硫化処理により全く新しい光触媒が得られたことがわかった.
8. 水溶液中におけるGreen Rustの酸化機構~鉄錆生成機構解明へのアプローチ
Fe(II)の酸化過程では,Green Rust (GR)と呼ばれる反応中間体を経由してFeOOHが生成する.酸化の条件により,αおよび/もしくはγ-?FeOOHが生成するが,その機構は,十分に明らかにされているとは言えない.これらは,酸化鉄微粒子の合成や鉄の腐蝕制御等の観点から興味深い問題である.本研究では純粋なGRを出発物質に,水溶液系における酸素による酸化過程をXRD,酸化還元電位(ORP),pH測定により追跡した.酸素分圧およびアニオン添加などの酸化条件と,酸化速度および生成物との関係から,アニオンの影響を中心にGRの酸化機構を検討した.
その他,本研究分野においては,多元物質科学研究所内の各研究分野や,金属材料研究所,工学部,他大学,あるいは企業の研究所などと積極的に共同研究の展開をはかっており,多元ナノ材料研究センターに課せられた社会的要請に応えるべく,研究を進めている.
|

