5 熱加工
ガラスの粘度は温度が高くなるにしたがって減少する。その粘度の温度による変化を図5-1に示す。ガラスの成形に適した粘度は104 ~ 107.6ポアズで、ソーダ石灰ガラスでは690~1000℃程度、ホウケイ酸ガラスでは820~1250℃程度のときにその粘度となる。したがって、ソーダ石灰ガラスの細工には都市ガス等に空気を混合させた炎を用い、ホウケイ酸ガラスの場合では酸素を混合させた炎を用いる必要がある。ホウケイ酸ガラスの細工を行う場合、ガラスを炎の中で1200~1300℃程度に加熱し、炎から出して成形する。成形している間にガラスの温度は下がり、820℃以下になると硬くなる。そこで温度が下がりすぎないうちに細工を手早く終えなければならない。細工に適した加熱を行うための炎の使い方やガラスの持ち方、また炎から出して成形を行い硬化するまでの間合いの取り方などは、細工を行ううえで特に重要なことである。

細工を行うための加熱方法について簡単に述べる。ガラスを急激に加熱すると熱衝撃のためにガラスが壊れることがある。そのため、酸素の混合割合を少なくした炎(図1)でゆっくりと予熱する。ついで、酸素の割合を増した炎(図2)で細工に適した温度まで加熱する。この炎の内炎と外炎の境がもっとも高温となる。そこで、局部的に加熱したいときには炎を小さくして内炎の先端で加熱し、広範囲に加熱したいときには炎を大きくして内炎の先端より少し上で加熱する等の工夫が必要となる。ガラスが軟化温度近くまで加熱されると炎の色が変化する。そのときの炎を(図4)に示す。ガスの量を少なく、酸素をより多くすると針状の炎(図3)ができる。この炎は前述した急熱法による切断の際にガラス棒を焼くときや、ガラスに小穴を開けるときに用いられる。



図5-2 ガラス管の持ち方
ガラス管を均一に加熱するために炎の中でガラス管を回転させる。ガラス管をスムーズに回転させるため図5-2に示したような持ち方をする。�@左手の小指と薬指でガラス管を支え、�A親指と人差指で回転させる。�B右手の中指の爪の上にガラス管をのせ、親指と人差指で回転させる。基本的には以上のような持ち方をするが、接合するときなど、図5-2-�Cのような持ち方をすることもある。ガラス管を回転させるとき、両手の動きのバランスがとれていないと、ガラス管が溶け出したときにねじれたり曲がったりすることになる。ガラス管を回転させるのはガラス管を均一に加熱するためだけでなく、ガラス管が溶け出したときに垂れ下がるのを防ぐためでもある。したがって、ガラス管を炎から出しても、軟化温度以下になるまで回転を続けなければならない。大径のものを加工するときはガラス旋盤を用いて回転を与え細工する。

図5-3 ガラス旋盤
次に熱加工の手順の主なものについて簡単に述べる。なお、図では炎で加熱する箇所を矢印↑で、切断する所は破線で示した。

1) 引き伸ばし
�@ガラス管を回しながら平均に溶かす。�A炎から出してまわしながらゆくりと引っ張る。完全に硬化するまで回す。
太い管を細工するときは太いままでは回転させにくいため、管を細く引き伸ばし持つところを作る。その部分を“足場”という。足場はそこを持ってガラス管を支えれるだけの太さと長さがあり、その軸がガラス管の軸と合っていなければならない。回転のさせ方が悪いと溶け方が不均一となり軸が合わなくなる。軸が合わないときには肩の所を加熱して修正する。足場を作るとき、加熱後炎から出して回転させながら少し冷め加減になるのを待って引っ張った方が太い丈夫な足場ができる。
2) ゴム止め
�@足場を作りその足場の肩から管径の1.5~2倍のところを細い炎で回しながら加熱し、少し引っ張りくぼみを作る。�A�@のくぼみから少し離れたところを加熱し�@と同様にくぼみを作る。�Bその中間を加熱し少し両側から押し縮めるか、空気を入れてふくらませる。�C肩を加熱し、引っ張ってなだらかにする。�D足場を切り取り、切り口を焼く。

3) 曲げ
�@曲げる部分を大きな炎で回しながら均一に加熱。このとき少し押すような感じで肉溜めをする。�A炎から出して円を描くような感じで曲げ、�Bすぐに空気を入れて整形する。ガラス管を固定し、大きな炎でゆっくり加熱してガラス管を自重で曲げる方法もある。
4) 接 合
 4ー1) 同径接合
4ー1) 同径接合
�@接合する部分を少し斜めにして回しながら加熱する。�A炎から出し両方の切り口を押し合わせる。�B継ぎ目全体をよく焼き溶かし、�C空気を入れて整形する。
4ー2) 異径接合
�@太い管を引き伸ばす。�A肩の部分を焼き、細い管と同径にしぼり、�Bを切る。�C4ー1)同径接合と同様に接合する。
4ー3) 側管接合
�@側管を付けるところを小さな炎で加熱し空気を入れて側管と同径に吹く。�A頂点のみを小さな炎で加熱し、側管と同径に吹き破る。�B側管を4ー1)の要領で接合する。曲げた管に側管を接合するとY字管ができる。
接合を行ううえで重要なことは二つの管の径を同じにすることと、接合部をよく溶かし合わせることである。管径が異なるものをそのまま接合すれば、穴が開いたり肉が溜まりすぎたりする。図5-11のように溶け合い方が不十分なものは細工後に破壊が起こりやすい。図5-12に示したように、継ぎ目が見えなくなるまで十分に溶かす必要がある。接合する管が太くて回しながら加熱(回し焼き)し整形するのが困難な場合、接合部をいくつかの部分に分けて加熱(部分焼き)し整形を繰り返す方法もある。
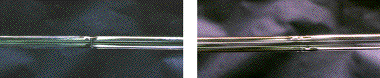
図5-11 溶着不十分 図5-12 溶着完了
 5) 口作り
5) 口作り
�@切り口をよく加熱し、肉を溜める。このとき、口が平らでなければコテで叩いて平らにする。�Aピンセットを差し込んで形を整える。このとき管を回し、ピンセットを動かないようにする。�B口を拡げるときはピンセットを斜めにする。
6) 底作り
�@足場の肩を加熱し、足場を取る。�A先だけを加熱し、ピンセットで肉を取る。�B底を加熱し空気を入れて整形する。底を平らにするときは、�C底を加熱し、底にコテを当てて平らにし、空気を入れて整形する。
7) 封じ込み
7ー1) 一端封じ
�@封じ込む内管を加熱してソロバン球のような小球を作る。�A外管をしぼり内管の小球に合わせて吹き破る。�B外管と内管を組み合わせ接合する。�C接合部が鋭角にならないように十分に溶かし、空気を入れて整形する。内管が中心にくるように注意する。
7ー2) 両端封じ
�@内管の両端を口作りの要領で少し開く。�A外管を内管と同径にしぼる。�B内管をガラス管等で支え、コルク栓等を使い外管と組み合わせる。このとき外管と内管の間に空気が通じるよう、また支えのガラス管で内管に傷を付けないように注意する。�C外管と内管を接合し、外管の足場を切る。�Dガラス管を接合する。他端も同様に封じる。

以上の基本操作を組み合わせて種々の器具を作ることができる。トラップ・コンデンサーの例を次にあげる。
